フランクフルター・アルゲマイネ紙 ユリア・エンケによる書評
彼女の全てがいつも皆を困惑させる

鋭い政治コラムで知られるロニヤ・オートマンが、自身のヤジーディとしての家族史に向き合う。小説第1作となる「Die Sommer」は、強い印象を残す物語だ。
ユリア・エンケ
「あなたの名前の由来は?アラブの名前でしょう?」。ロニヤ・オートマンの小説「Die Sommer」で、ミュンヘンのドイツ語の先生が生徒のライラにこう尋ねる。ライラは首を横に振る。「イスラム教については、きっとライラが何か説明してくれるでしょう」と社会科の先生は言って、ライラを期待に満ちた様子で見つめる。ライラを誕生会の後に車で家まで送ってくれた同級生の母親は、ライラにこう尋ねる「あなたたちはラマダンの時に断食するの?色々な文化の間で育つって、難しいんじゃないかしら?お父さんはきっと厳しいんでしょうね?お母さんはスカーフをかぶっているの?」。ライラは答える。いいえ、私たちはイスラム教徒ではありません、いいえ、私たちはアラブ人ではありません、いいえ、私たちは家でお祈りはしないし、ラマダンの時に断食もしません、でも、私の祖母と叔母はスカーフをかぶっています。そうした答えは、さらなる質問を呼ぶことにしかならない。ライラが、私たちはヤジーディです、と言えば、その人たちはライラが何のことを言っているのかもうすっかりわからなくなる。「ライラの全てが、いつも皆を困惑させるのだ」とオートマンは書く。「近くのパン屋さんも、歯医者さんも、薬局の店員さんも、学校の先生も」。ライラが「父はクルディスタン出身です」と言えば、皆は「クルディスタンは存在しない」と答える。ライラは「父はシリア出身です」と言い、父のことを考えて自分を恥じる。
1993年にミュンヘンで生まれ、ミュンヘンで育ったロニヤ・オートマンは、他の人たちを困惑させるというライラの体験を共有している。オートマンの母はドイツ人、父は1980年にシリア北東部からトルコを経てドイツに逃げてきた無国籍のヤジーディ・クルド人だ。だが、周囲の困惑は、同時にオートマンの資本でもある。そこから汲み出されているのがオートマンの政治的な熱意、生産性、しっかり見つめることを拒む多くの人たちに対する怒りなのだ。今週、ベルリンで会った時に、オートマンはこう言った。「ドイツでは、ヤジーディと聞いて連想するのはせいぜい名誉殺人くらいです。他のことは見えないことになっているのです。すべて、これほど身近なことなのに」。
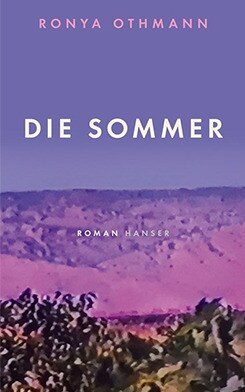
© Hanser Verlag
右にも左にも噛みつく
オートマンは、アーティスト・作家であるツェミレ・ザヒンと共同で「taz」紙のコラム「オリエント・エクスプレス」を執筆していた。8月中旬、連載最後の記事の一つでオートマンは、6年前にいわゆる「イスラム国家(IS)」の戦闘員がシンガルに侵攻した際に行ったジェノサイドを取り上げた。シンガルはイラク国内に暮らす少数民族ヤジーディの非公式の首都であった。「彼らは男性と高齢の女性を射殺し、女性と子供をIS戦闘員の奴隷とするため連れ去った。男児は全員少年兵として使われ、大人の女性と女児は強姦された」。そしてそれは、ドイツにいる私たちにも関係することだ、と。フランクフルトでは今、タハ・アル=Jが裁判にかけられている。この人物は、5歳の女の子とその母親を買い、2人をファルージャの自宅で妻(IS信奉者であるドイツ女性ジェニファー・W)と共に搾取した疑いで告発されているのだ。タハ・アル=Jは、罰としてこの女の子を灼熱の中で窓に鎖で縛りつけて脱水死させたという。ジェニファー・Wに対する裁判はミュンヘン上級地方裁判所で行われている。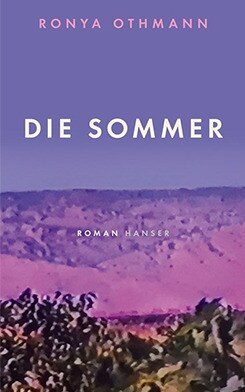
ジャーナリストしてのロニヤ・オートマンの文章には心を打つ鋭さがある。その視点がとても興味深いのは、イデオロギー化に対する戦いの中でオートマンが右にも左にも噛みつくからだ。「イスラム批判」が外国人嫌悪の口実として使われるところにも、また、イスラム主義を「反植民地主義的な抵抗の一部」と相対化して片付けようとするところにも、オートマンのペンは切りつける。「共に右翼に抵抗しよう」という横断幕の元に幅広く戦線が組まれ、例えばムスリム中央評議会(ZMD)が筆頭署名者であった#Unteilbar-Bündnis(不可分連合)が登場した時には、オートマンはZMDに欧州トルコ文化協会連合が加盟していることを指摘した1人だった。同連合は極右の「灰色の狼」の一員だ。また、イスラムセンター・ハンブルクも同様である。同センターはイランの最高指導者の指揮下にあるのだ。
血が滲み出てくる傷口のように
2014年、ISがイラク北部のヤジーディの村で暮らす人々を襲撃した時、オートマンはすでにこの小説に取りかかっており、シリアにある父の出身の村について覚えているありとあらゆることをまとめていたところだったと言う。一神教を信仰するがキリスト教徒ではないヤジーディは、イラク、トルコ、シリア北部に暮らす宗教的少数民族である。まさにそのシリアに、小説の主人公のライラ同様、オートマンは毎年行っていた。祖父母のもとで夏を過ごすために。ただ、そこで過ごしたいくつもの夏を思い出すことは、長いことなかった。「Die Sommer」のなかでオートマンはこう書いている。「追想が始まったのは、2011年になってからだった。いや、違う、むしろそのすぐ後だった。2011年はまだ、革命の年だった。ニュースと期待感に溢れた年、黄金の未来が私たちの前にあった年。自由、民主主義、人権が」。追想は、アラブの春の後に始まった。「大量殺戮、爆撃、破壊と共に。追想は破壊と同時に進行し、破壊の後に続いた。ショックを受けるたびに悲しみが訪れ、その悲しみは次のショックによって再び押し流されていった。終わることなど何一つなかった。記憶はどんどん広がり、蔓延し、もはや止められなかった。まるで傷口のように、とライラは思った。そこから血が滲み出してくる傷口のように」。
地雷には軽すぎる七面鳥
そうしてオートマンはこの小説を書き始める。オートマンの最初の小説であるこの作品には、デビュー作とはとても思えないほどの見事な風格がある。「父の国」で過ごしたいくつもの夏。その村で、その女の子は一日中おばあちゃんの後ろにくっついて回る。高い寝台で数珠のように並んでいるいとこたちの隣で眠る。タバコの葉の収穫を手伝う – これら全てが、そっと手探りするような言葉で描かれる。それはオートマンのジャーナリストとしての舌鋒鋭い文章とはほとんど対極にある。文学として書く時には感覚的なディテールを大切にしている、とオートマンは言う。「夏の間そこで寝ていたマットレスがどんな素材のものだったか。どんな匂いがしたか。ひとつの世界を甦らせることができるのです。ヤジーディは口承で全てを伝えています。本はありません。祖父母の世代は、ほぼ全員、読み書きができません。人が死ねば、物語も死ぬのです。文学は、これらの物語が失われないよう、運ぶことができます。小説の中であれば、誰かがアサドのスパイとして働いている場合にも、ジャーナリストとしての文章を使うよりもその複雑さを文学的に上手に語ることができるのです。ライラの叔父はスパイだとして非難されますが、ライラはその叔父さんがそもそも好きなのです。それが何を意味するか、また、ライラがそれに対して取るべき態度を決めるのにどれほど苦労するか。そういうことを物語ることができるのです」。オートマンは「Die Sommer」にも口承の伝統を取り入れている。ライラがシリアで過ごした子供時代の夏休みの思い出を、ライラの父親が語った過去の物語と結びつけるのだ。この手法で浮き上がるのは、テル・カトゥン村を通じて見えてくる国境地方の政治的な歴史である。父親は言う。昔、人々はよく、トルコに向かって夜に国境を越えたのだよ、と。商売をしている彼らには、国境の反対側に家族や友人がいたのだ。しかし、彼らの間には対人地雷や対戦車地雷が埋まる地雷原が横たわっていた。地雷が爆発すると、その爆発音は村で聞こえる。死者。父親の物語の中では紙ナプキンの上に小さな十字架で描かれる死者。地雷には軽すぎたのは隣の家の七面鳥だけだった。所有者があっけにとられて見守る中で、七面鳥は(とても愉快なシーンだ)永住すべくトルコへと渡っていく。
暴力の痕跡
ライラはヤジーディのコミュニティの外で結婚すれば、コミュニティから排除される恐れがあることを知っている。ライラがそこにいるのは幸いにも夏の間だけだ。自分の息子の嫁に、と、ライラに目をつけている隣人がすでに1人いる。ライラは、周囲の手配で結婚した叔母の様子をつぶさに観察し、全く別のもう1人の男が叔母を観察していることも知っている。ライラは他の子供たちと一緒に一度だけ村の学校に行ったことがある。椅子も机もない学校で、子供たちは暖房のための炭を自宅から持って来なければならない。教室は空っぽだが、どの教室の壁にも大統領の写真が飾ってある。「大統領の目はいたるところに光っている。大統領を見ると、ライラはその目つきに恐怖を感じた。大統領の目には、ライラが何を考えていて、家族が大統領について何を言っているかが見えるのだ、とライラは思った」。ライラの父親は、バシャール・アル=アサドの目は、それがこちらには見えないところにすらある、とライラに言った。まさかと思うような人たちこそが、大統領の目なのだ、と。国の中に、信用できる人はいないのだ、と。父親が秘密警察に呼び出されたのは、フセイン叔父の発言のせいだった。父親がそれをライラに話したのは、ドイツでのことである。父親はライラに、トルコの刑務所でついた傷跡も見せる。電気ケーブルで叩かれ、腕に火のついたタバコを押し付けられた跡。シリアからトルコを経由して逃げた父親の話と、それが残した暴力の痕跡は、この作品の中で最も強い印象を残す一節の一つだ。ミュンヘンで、同じクラスのエムレがライラに「あなた、トルコ人?」と尋ねる。ライラは父親の傷跡のことを考え、そして首を横に振る。ミュンヘンのライラの友達、周囲にいる人々は、シリアの戦争に本当に関心を持っているわけではない。何かを聞いてきたことは一度もないし、ライラの親戚の様子を尋ねてきたこともない。しかしライラの家では、ずっとアラビア語放送が流れている。まさにそれがライラを疎外に追いやり、同時に、記憶と父親の物語を通じて、今そこで戦争の中にいる人々の物語が自分のものになっていく。これが「Die Sommer」の名人芸だ。なぜなら、シリア側の家族に近づいていくのはライラだけではない。私たちも同じことをすることになるからだ。
オートマンは現在、ライプツィヒに暮らし、ライプツィヒの文学研究所で学んでいる。この課程はいずれにしても最後まで修めたい、とオートマンは言う。あとは修士論文を書くだけだ、と。「修士論文はどのようなものに?」と尋ねると、小説をひとつ書かなければならないのだと言う。しかし小説なら、ちょうどひとつ書いたばかりでは?「そうなのです。でも、未発表の小説でないといけないの」。つまりオートマンは、第2作となる小説にもうすでに取りかかることができるのだ。第1作を読んだ人は、シリア北東部での数々の「夏」をきっと忘れないだろう。